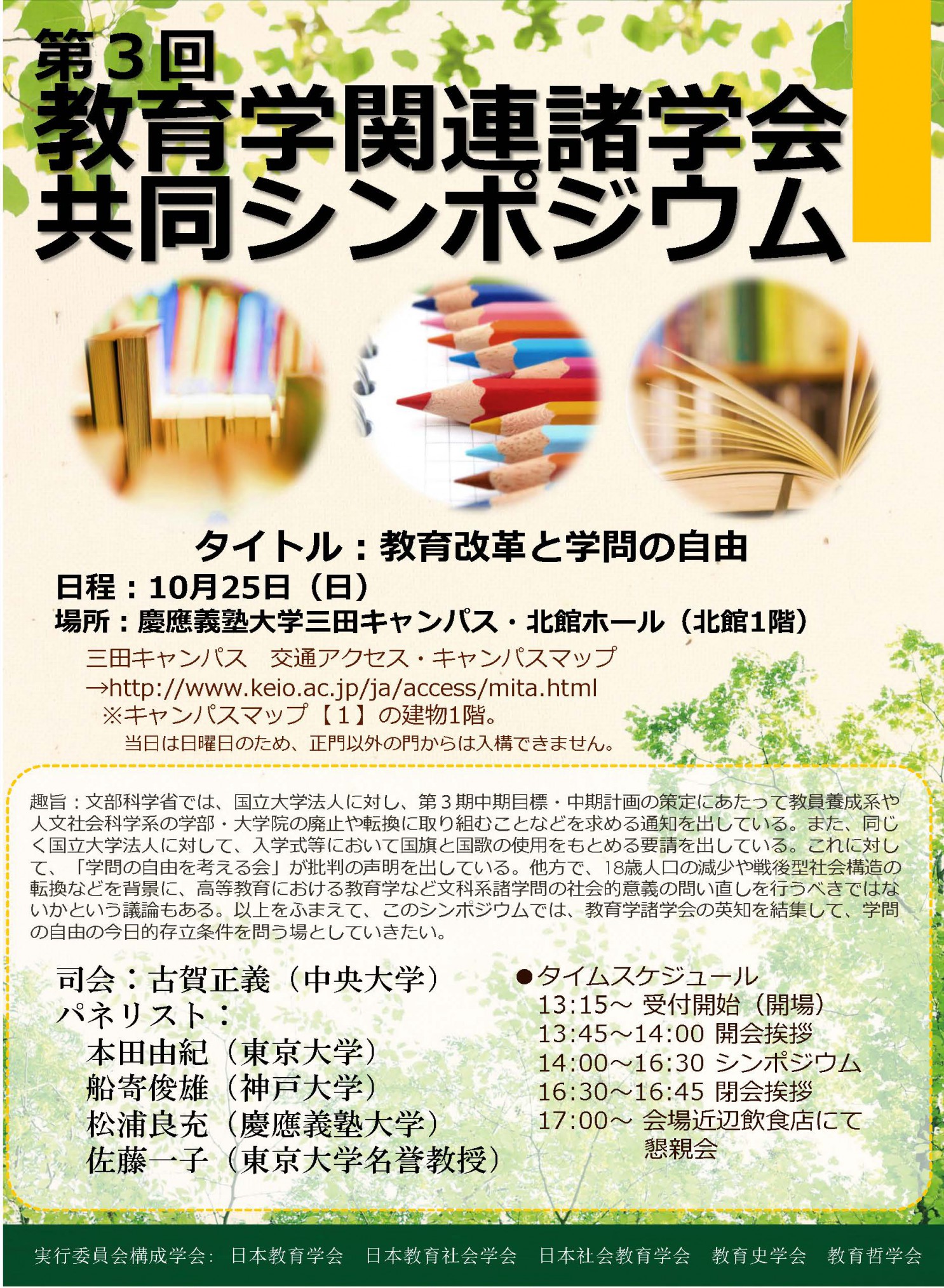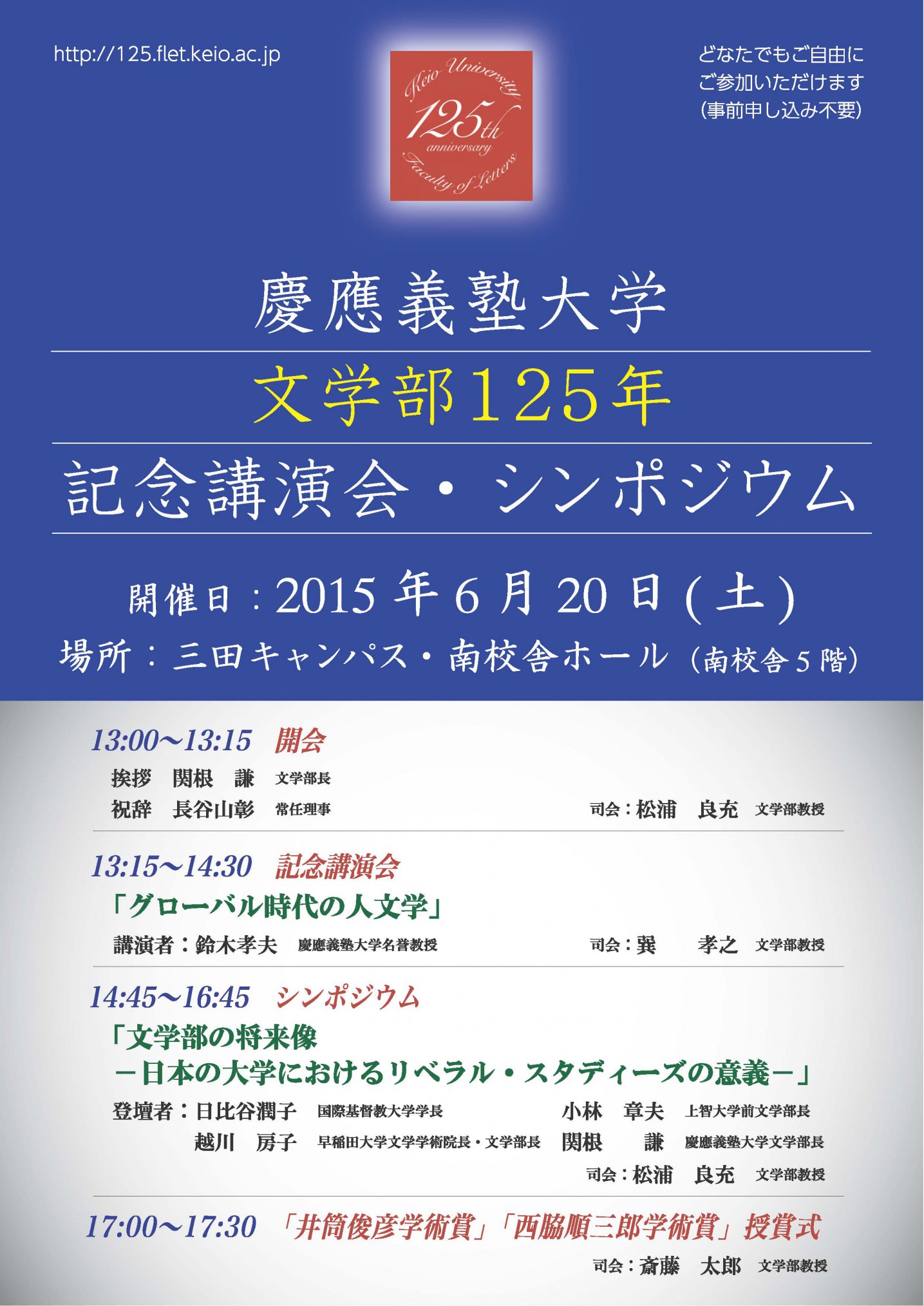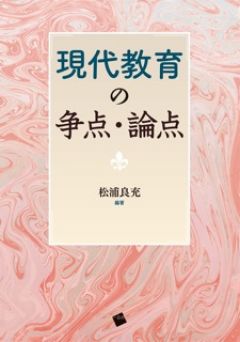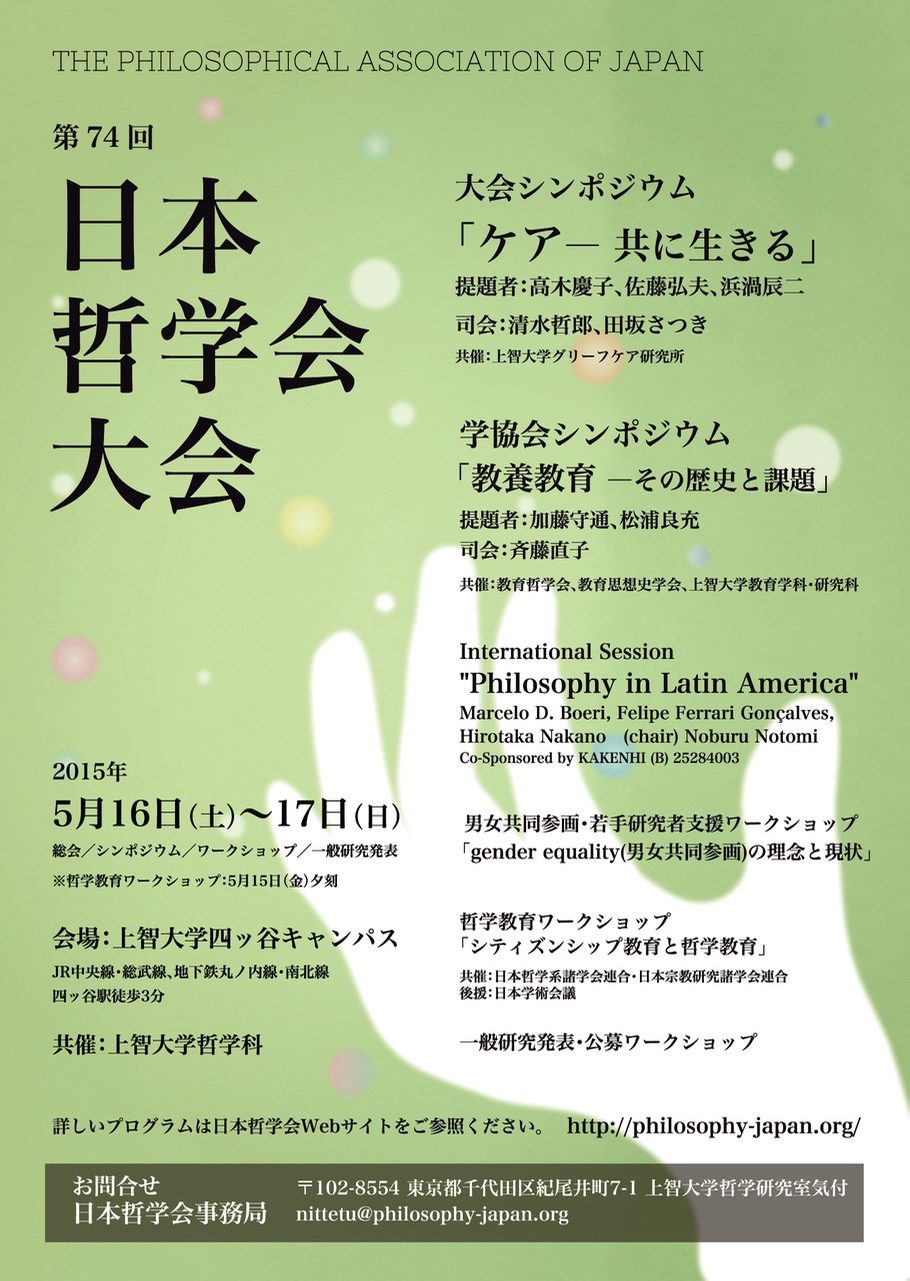提 出
4年生:2015年9月22日(火)23:59【厳守】
3年生:2015年10月13日(火)23:59【厳守】
本サイトの「メディア」にアップロードする(ファイル形式は、原則としてMS -Word文書ファイルとする)。
☆コメント締切は、当該論文「夏課題検討」発表の前の週のゼミ開始時(例:10月7日発表予定者の分のコメントは、9月30日ゼミ開始時までに)。4年生はゼミ合宿の際に、相互に相談をして発表日を確定してください。
課 題
≪3年生対象≫
0.以下にあげるものをはじめとして、<論文の書き方>に関する参考書を複数通読すること。
1.研究課題を決める(卒論のテーマを意識しつつ)。
2.その課題に関連する参考文献(少なくとも50点)を検索し、リストを作成する。
(単行本、論文、資料など)
3.参考文献のうち、少なくとも10点について精読し、ノート(カード)をとる。
(ノートをもとに、それらの要約をまとめる。)
4.精読した文献から、設定した課題に関する現在の研究水準として、
–a) なにがどこまで明らかにされているのか、
–b) 対立する考え方(論争点)としてどのようなものがあるのか、
–c) 今後の研究課題としてなにが残されているのか、について確認する。
5.上記4に基づいて、自分の研究は、「なにについて」「どこまで」「どのように」して明らかにしようとするのか、
について考えをまとめる。
6.以上をふまえて、8,000〜12,000字程度の【論文】をまとめる。
論文には少なくとも、以下の諸点が含まれていなければならない。
–a) テーマ(タイトル)
–b) テーマの概要(上記5)
–c) なぜそのテーマを課題とするのか
–d) 先行研究の検討(上記4)
–e) テーマの具体的内容・展開
、今後の研究の見通し・計画・予定
–f) 参考文献リスト
≪4年生対象≫
0.The Craft of Researchの内容についてよく復習すること。
1.卒業論文の下書きにあたるものを、40,000字程度にまとめる(表題・アブストラクト・目次・注・参考文献一覧をつけたもの)。☆ただし字数を増やすことに腐心して、引用の継ぎ接ぎを重ねたノートのような「論文」にしないこと。字数は少なくてとも、論や章の筋立てが明確なものにすること。
2.章の構成の仕方、註のつけ方、参考文献の表記の方法などについては、各自、以下に示すような<論文の書き方>に関する書物を複数参考にして正確な様式を用いること。
<論文の書き方>に関する参考文献
※レポート(論文)の執筆にあたっては、必ず論文の書き方についての参考書を参照し、形式・内容の両面において学術論文の水準を満たすこと。
1.斉藤孝・西岡達裕『学術論文の技法』【新訂版】、日本エディタースクール出版部、2005。
2.櫻井雅夫『レポート・論文の書き方 上級』慶應義塾出版会、1998。
3.白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書き方』ミネルヴァ書房、2008。
4.高崎みどり編著『大学生のための「論文」執筆の手引―卒論・レポート・演習発表の乗り切り方―』秀和システム、2010。
5.花井等・若松篤『論文の書き方マニュアル―ステップ式リサーチ戦略のすすめ―』有斐閣アルマ、1997。
6.戸田山和久『論文の教室―レポートから卒論まで―』NHKブックス、2002。
なお、上記参考文献は、あくまで論文執筆のための「参考」書である。必ずしたがうべきマニュアルのように扱うことのないように、注意すること。
註や文献の表記の仕方
※引用・参考文献の出典の表記の仕方には、大きく2種類ある。これらの方式を混合させないこと。
1.脚注/巻・章・節末注(Notes and bibliography)方式:本文中の該当箇所に右肩に小さく番号をつけ(括弧をつけることもある)、それに対応して注をつける。
2.著者名・発行年(The author-date system)方式:本文中の該当箇所に(著者名 発行年、頁数)を入れ込み、巻末に参考文献一覧をつけ、照合可能とする。文献出典以外の注は、1と同様の方式でつける。
なお表記方法の細かい点については、<論文の書き方>の本でも必ずしも一致していないところもある。一つの論文のなかで、整合性(統一)がとれていればよい。
※英文文献の表記に関しては、The Chicago Manual of Style: The Essenntial Guide for Writers, Editors, and Publishers. 15th edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2003. の主として16-17章(pp.593-754)を参照すること(最新版は、16th edition)。上記の1と2の区別についても詳細な約束事についての記述がある。それらは、日本語の註 や文献表記にもある程度応用できる。(大学院進学予定者は、一度は目を通しておくこと。)現在は、The Chicago Manual of Style Online (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html)としても、手軽に利用できる。
以上